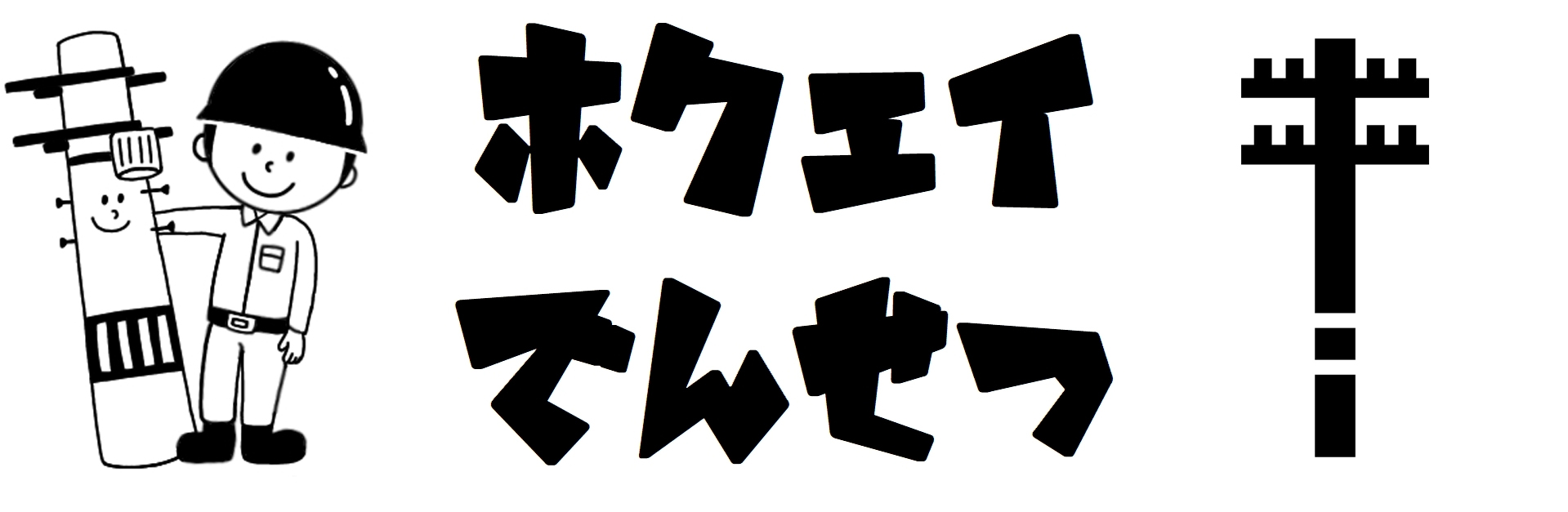だいぶ暖かくなり、春へまっしぐらな今日この頃。期末なので忙しいにも関わらず、なぜかいろんなものが壊れます。機械は壊れるけど仕事は待ってくれないわけで、急いで直す必要があるのです(笑) 今回は(も?)壊れたものたちを直すべく奮闘した様子をお届けします!
まずはこちら。建柱車のウィンチを巻くための減速機が収まるギアボックス、それのシャフト側のオイルシール(パッキン)が外れた件。これは 以前の記事 で応急処置をした後、心配だったので整備工場に持って行って本修理してもらったのだが、再びポロリと外れてしまったもの。本修理とはいえ、機械自体がかなりくたびれているのでガタが大きく、機械を激しく使うとオイルシール自体をシャフトが押してしまい、外れてしまうと予想。


このオイルシール、ギアの潤滑油を封じ込めておくという重要な役割があるもの。なので、これが外れたまま使い続けると短時間でギアが焼き付いてしまう恐れがある。なお、ウインチドラムにはブレーキも付いているので、万が一ギアボックスが壊れたとしても吊り荷が落ちてしまうということはない。


ギアボックスと車両本体をつなぐボルトはわずか5本。しかも、片側だけしか固定されていない。歯車と並行方向へは鉄板の張力で十分な強度があるものの、垂直方向への荷重は固定部の鉄板厚の強度とボルトのみで持たせている構造だ。トン単位の荷重がかかる場所というのを考えると、最初から設計自体に少々無理があるような気がする・・・。
試しに電柱を吊ってみると、ギアボックス自体がトルクの反動で微妙に動くのが確認できた。新しい状態ならばいざ知らず、ここまで古くなってくると片側のみ固定で板厚が6mmというのは、やはり強度的に厳しいのかも知れない。
そんなわけで急遽、当て物を追加してギアボックスの固定を強化することに。












今回も応急処置としての位置づけなので、後で本修理に持って行く予定。試しに電柱を吊ってテストしてみたところ、これまでのようにギアボックスが動くような挙動はなく安定している。しかし、これが外れると毎回作動油まみれになるの、なんとかならないのかな(笑)
スチール社のチェーンソー「MS 240」の不調
次はこれ。アンドレアス・スチール社のチェーンソー「MS 240」という機種だ。結論から言うと、直らなかった。このチェーンソー、実は15年ほど前(もっと前かも?)の古い機種で、エンジンがなかなか掛からず、何回か初爆はするもののすぐに止まってしまうといった症状。
整備前の状況でスターターを引っ張ってみるが、圧縮がスカスカで嫌な予感・・・。これはシリンダかピストン、またはその両方が摩耗していると考えて良さそうな感じ。
まあ、ものは試しということで、まずはバラして整備してみます。






プラグがカブりぎみなので、キャブ調整が必要と判断。本体に貼ってあるシールは文字がかすれて読めない。うろ覚えで回すのも怖いので、三光クボタさんのホームページから取説をダウンロードして確認。


MS 240のキャブレター調整は、H(高速側)とL(低速側)を両方とも右にいっぱいまで締め(強すぎないように注意)、所定の回数分左側に戻すというオーソドックスなもの。本体のシールは文字がかすれているが判別くらいはできそうな感じ。
調べた結果として、手元の機種の戻し回数は
- Hが反時計回りに3/4(4分の3)回転戻し
- Lが反時計回りに 1 回転戻し
と分かった。
いつもの流れでは
- LとHの両方を時計回りに締め込んだ後、規定値分戻す
- 始動してアイドル状態にする
- エンストする場合アイドリング調整ネジでアイドリングを少しだけ上げる
- アイドリング回転を見ながら回転が上がる方向にLを回して微調整
- アイドリング回転が一番高くなったらLをほんの少しだけ戻す(経験上、混合比が理想よりも少しだけ薄くなったときに一番回転が上がる傾向がある。トルクは減るけど)
- アイドリング調整ネジを少し戻す
- すると、LとHのつながる中間付近にも影響するので、スロットルを開きながらHとLの兼ね合いを見ながら、回転が滑らかにつながるように微調整
- 再び4の手順に戻り、スロットルを開いたときに回転が安定して上がる部分を探す
という手順を、回転の上がり方、音と臭いなども見ながら総合的に判断し、何回か繰り返し調整している(自分の場合)
しかし今回は、規定値に合わせた後、圧縮がスカスカで何をしても始動しない。プラグの様子から見て燃料は送られているようだし。総合的にピストンとシリンダの摩耗が一番怪しいと判断。オーバーホールして使い続けるほど新しくないし、今回は断念することにした。残念!


ちなみに、バッテリーをたくさん持っているなら充電式チェーンソーがすごくお勧め。エンジン式チェーンソーは燃料を使い切る必要があるし、今回のようにエンジンが掛からない場合がかなりある。
何より、高いところや電線の近くでスターターを引っ張るのはそれだけで危険の伴う作業だし、スロットルを握らないと掛からない調子の悪いチェーンソーなんかだと、高所作業車のバケットの中で急にチェーンが回って危険でもある。その点、スイッチを入れれば常に使える充電式チェーンソーって、もの凄い信頼感があるよね(笑)
会社の冷蔵庫、旅立つ!
ホクエイ電設の事務所には、我々の喉を潤してくれるありがた~い、小さい冷蔵庫(1ドア)があります。霜で凍り付いてて不便だったこの冷蔵庫、見かねた若手2人組がこのたび掃除してくれまして・・・。
ええ、ハイ。
結果として、壊れました(笑)


画像はないけど、電工ナイフとマイナスドライバーで霜をこそぎ取っていた時に事件は発生。ぷしゅーという音と共に触媒ガスが抜けて冷えなくなってしまったとのこと。そういえば、自分も昔同じ事した覚えがあるなあ・・・。


タイミング良く(?)いらなくなった冷蔵庫を社長が持ってきてくれたので、冷えた ビール 飲み物を飲むことができています。ちなみに、この時に社長が持ってきた冷蔵庫は2つ。そのうちの1つは自宅用にいただく事ができました。


その他、細かい修理など
主に2月と3月中に修理したものなどをまとめて載せておきます















実際は、もっと壊れたものがあるんだけど、書ききれないのでまたの機会に。っていうか、いろいろ壊れすぎ(笑)