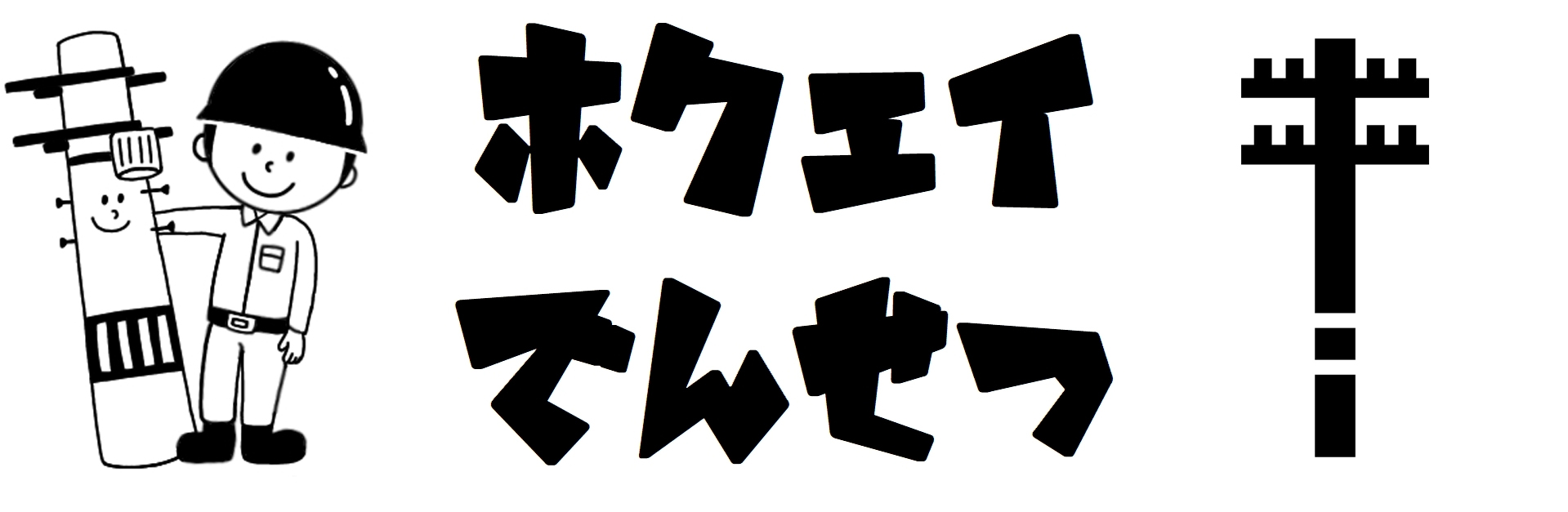各地で線状降水帯が多発するようになった昨今、各地で発生した洪水や土石流による被害を受け、市民の間にも強い危機感が芽生える中、被害を少しでも防ぐために自治体でも防災訓練を行う機運が高まっています。
「災害復旧において微力でも力になれれば」と常に考える我々は、貴重な訓練を間近で体験できる機会にはできるだけ参加したいところ!
そんなわけで今回は、2025年8月31日に東京都主催で行われた、東京都・羽村市・日の出町合同総合防災訓練に参加したときのようすをお届けします!
東京都主催の防災訓練で使われた「本物の木柱」
「防災訓練で使う、本物の木柱が欲しい。 リアルさを追求するために」
こんな1本の電話から始まった、今回のプロジェクト (笑)
なんでも、コンクリート柱は手に入るが、木柱が手に入らないとのこと。(木柱とは、木で出来た電柱のこと)
幸いにも、先週まで現場に建っていた木柱があり、それを使うことに。 この木柱は、乾燥させた杉の丸太をクレオソートという防腐剤にぶち込み漬け込んだもので、昭和50年代に製造されたもの。 電柱屋の間では、通称「クレ柱」とか呼ばれている。 少々薬剤臭いので、電柱屋からは好かれることがないのが特徴だ!


防災訓練の場所
今回の防災訓練の場所は、「東京都羽村市」にある「宮の下運動公園」いうところ。 位置的に言うと八王子の北側、多摩川沿いにある広大な運動公園で、付近にはのどかな田園や閑静な住宅地が立ち並び、山と川と平地が混在する、風光明媚なところだ。 (星印が宮の下運動公園)

今回の防災訓練は、「多摩東部を震源とする首都直下地震(マグニチュード7.3)」を想定し、その特徴は以下のもの。
・防災への関心を高める都民参加型の訓練及び都民の安心感醸成に資する訓練
・行政・機関の災害対応能力向上に向けた訓練
・能登半島地震を踏まえた、孤立地域の発生を想定した訓練等
詳しくは下記「東京都防災ホームページ」にて。
令和7年度 東京都・羽村市・日の出町合同総合防災訓練の実施について
事前の準備
もちろん、防災訓練の当日に資材を運び込むわけではなく、かなり前から事前に準備をしておきます。
ここでは、一般の方が間近で見ることのできない会場の様子を少しだけご紹介!




河川敷を傷めないように用意されたプラスチック製の敷板は何と1,000枚以上! これだけの資機材を用意できるイベント会社は、銀河系広しと言っても、そうはないでしょう!(今回は株式会社ヤマチコーポレーションさん) 超本気モードの規模のデカさに戦慄だ!


スゴイのは規模の大きさだけではない! 用意された倒壊家屋もやたらとリアルに作られていて、「ここまでするか・・・?」というレベルにドン引き (笑) 下の画像左側に見える工場は実際の町工場の写真が印刷されたもので超リアル!

いざ、防災訓練へ向かう!
大がかりなセットを使った今回の防災訓練(救出救助訓練)が行われるのは、2025年8月31日の15:00から。 15:00まで時間がありすぎたので、会場までに立ち寄った場所を一部紹介。 幸いにも、この日は日曜日。 時間をつぶすのは苦ではなかったぞ!
八王子インターを降りて走ること20分ほどで見えてくるのが、かの有名な「米軍横田基地」。 立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町の5市1町にまたがる国内最大級の米空軍基地だ。 当時、福生(ふっさ)という村の名前が米国人にとって言いにくかったことと、聞く側の日本人も福生ではよく聞き取りにくかったという理由から、付近の地名をとって横田基地になったという。
今回の防災訓練でも参加した米軍。 消防車が大きすぎて、会場に入るのに何度も切り返し、ようやく運び込んだ、とのこと(笑)


米軍横田基地の近くでは、独特な雰囲気があることに気づく。 そう、なんとなくアメリカ臭漂う雰囲気があるのだ(アメリカ行ったことないけど)



横田基地前の国道16号線から少し離れると、急に日本に戻ってきた感覚になるのが不思議。 まあ、もともと日本なんだけど。


実は「モリパークアウトドアヴィレッジ」にも寄ったんだけど、超長~くなるのでまたの機会に。


やたらと厳重な警備
防災訓練会場へと車を走らせる。 稲穂垂れる田んぼでイチャつくカップルを過ぎ、つ、着いたあぁぁぁ! 現地にようやく到着! そこで目にしたものは・・・。 やたらと厳重な警備だった!


親子連れが多いので穏やかな空気が漂うなか、厳重な警備が対照的! こう警察官が多いと、悪いことをしているわけではないのに、なぜかキンチョー。 ふ、不審者じゃないっすよ、ホント!


規模のデカさにびっくりした!!
今回の防災訓練は、東京都が主催するだけあってかなりの規模! 参加するのは、都庁の職員や警視庁を始めとする警察官、救急隊、消防隊、レスキュー隊、自衛隊、東京都建設局、米軍横田基地消防隊、JAF、献血公共事業団、東京電力、NTT東日本、東京都LPガス協会(順不同)などなど、まさに圧巻のひと言! あ。もちろん、都知事も来られましたよ!

見たことない特殊車両のオンパレード。 もうね、人と車両の数がスゴイのなんの。 地方在住の我々には見ることのできない風景。 なんか警察官もデカいし・・・。 東京都、すげえ。





市民参加型の展示・体験訓練
隊員しか入れないエリアのすぐ隣では、一般市民が参加できる体験型の防災訓練が行われていた。 そこでは数々の特殊車両の展示が。 身の回りにある身近なもので担架を作る体験などもあったぞ!






企業出展のブースでは、過去の災害事例と、身を守るための防災グッズなどが展示されていた。






事前予約することで、消防車のはしごに乗ることもできた今回の防災訓練。 用意されたはしご車は30m級と言われるもので、地上高30mまで伸びるシロモノ。 我がホクエイ電設の高所作業車は地上高14mまでしか伸びない(それでも怖い)ので、異次元の高さだ!


米軍基地のデカい消防車
横田基地から来たものの、曲がれなくてやっとの思いで搬入されたという(笑)、バカでかい消防車を見てみよう!






全体的に見てみると、国産の消防車がいかに「省スペースと効率性、高性能とメンテナンスのしやすさの両立(要はハード面)」を重視しているのに対し、米軍の消防車は「消防隊員のストレスをどれだけ減らせるか(こちらはソフト面)」に焦点が当てられている気がした。 これも国民性の違いなのかもしれない。



救出救助訓練の本番
いよいよ救出救助訓練が始まるッ!
鳴り響くサイレン! 轟音とともに入場する数々の特殊車両、そして駆け足の隊員たち・・・!


自衛隊や消防隊員、警視庁の救助部隊などが連携し、救出救助訓練が進んでゆく。 倒壊し土砂に埋もれた家屋の屋根をチェーンソーで切断し、中の人を担架に乗せクレーンで救出する訓練や、流れ出た土砂を重機を使って取り除く訓練などが行われた。 どのチームも手慣れた動作だ!


あれ? そういえば、木柱はどこで使われたのかな・・・? あ、あそこにあった! どうやら、地震で倒れた木柱が道路に積み重なり救助の支障になっている、という設定のようだ。 警視庁の特別な重機(最大 100m 離れたところからリモコンで操作できる重機)を使い、木柱を安全に取り除く、という訓練で使われていた模様。 う~ん。こんな大舞台で活躍するなんて。 木柱よ、父さんは鼻が高いぞ!
救助訓練もいよいよクライマックスに!
どこからともなく響く轟音。 救助訓練の締めは、ヘリ3台を使った救助ならびに放水・消火訓練だ! ヘリから吹き下ろす暴風と、多くの消防車による同時放水で映画顔負けの大迫力! これは見なきゃ損だ!


普段から鍛え上げられた隊員たちがキビキビと動き、ハードな訓練をこなしてゆく。 ヘリで吊るされてゆく隊員なんかスリル満点だろう。 俺なんて冷蔵庫のプリン見つけても「賞味期限、大丈夫かな」って迷う程度のスリルしかねぇよ。

水車のあるカフェに寄った
さて、待ち時間の間に立ち寄った素晴らしいカフェもご紹介。
防災訓練会場から歩くこと、わずか30秒。 メダカの泳ぐ用水路を過ぎた田園風景のなかに、このカフェはある。 元々の古民家をカフェに改装したもので、水車が好きすぎる前の家主さんが水車を自作して取り付けたそう。 凄いメンタルとパワーである・・・。(ゴクリ)





大正2年(1913)から昭和16年(1944)にかけて「大菩薩峠」41巻(未完)という超大作を執筆したことで有名な小説家「中里介山(なかざとかいざん)」さんが、羽村市の水車小屋で生まれたということも背景にあるのだろうか。 並々ならぬ想いが伝わってくる、隠れたパワースポットだ。


ちなみに、中里介山さんの実家もこの付近にあり、墓はこの水車小屋から10分ほど歩いたところにある「禅林寺」にある。 使われた石材は、氏の代表作にちなんで大菩薩峠から運ばれたとのこと。 すべてに優しさやリスペクトの精神が感じられるエピソードとなっている。


巨大な水車と古風な建物、センスの良いインテリアが目を引くが、まず、ここは料理がスゴイ! 主にご近所で収穫されるお米や有機野菜などから作られる料理は、素材本来の風味を大切にする本格的なもの。 これはまるで都内のカフェで出るクオリティー。 嬉しすぎるぞ!


展望の良い2階席がおすすめだが、昔ながらの作りで階段がやたらと急だ(おばあちゃん家みたいに)。 お酒を飲む人は転がり落ちないように気を付けよう!(笑)


おいおい…こんなに野菜がうまいなんて聞いてねぇぞ。 俺の舌、今まで何してたんだ? 50年も無駄にしてた気分だわ。 このスープカレーも、反則級だろ。 酸味と甘みのバランスが、まるで初恋の味だよ。 ああ、俺もこの野菜みたいにフレッシュに生きたかった…いや無理だな、もうしおれ気味だし。

この日注文したのは、「豚の角煮丼」と「スープカレー」。 その日の朝に収穫された新鮮な野菜が、しっかりと下ごしらえして作られていた。 飲み物を含め、どれもが美味しいので本当にオススメ! あ。最後に大事なこと言い忘れてた。 ここのオーナーシェフさんが素敵な女性で、会いに行くだけでも価値があるぞ! (筆者は実際に、この後に何度も通っている。 片道2時間かけて千葉から(笑))
帰りの道も割とヤバかった
木柱を使った防災訓練が無事に終わったところで帰宅するわけだが、帰宅時も割と濃かった ので、そちらも見てみよう!
防災訓練の会場を出て、まずはインターに向かう。
信号が赤になり、横断歩道を続々と渡る馬。 馬だよなあ。
誰も驚かない。 それが一番こわい。 ……もしかして俺、疲れているのかもしれない。


馬の渡る横断歩道を過ぎると、「食堂くるくる」がある(寄れなかったけど)。 このお店は、とんねるずの番組で紹介され、「きたなシュラン」(見た目は汚いけれど、料理は美味しい飲食店)で星2.5を獲得したお店。
星2.5には理由があり、
ロケで生野陽子が座る予定だった席に、店主が「ご飯少なめのカツ丼」を置く
↓
その席に木梨が座ってしまい、誰も気づかず「ごはん少なめのカツ丼」を木梨が食べる
↓
木梨「うまいけどごはんの厚みが薄めじゃん! なので星半分減らしてみました」
↓
というオチで星2.5になったとのこと。


さらに高速入口に向かって進む。 見えてきたのは、大量の「きぬた歯科」さんの看板が目印になる、インター手前の大きな交差点。 少し走ると、そっくりなポーズでどっちが真似したのか? よく分からない看板もあるぞ。



首都高に乗っても安心はできない! そう、ほくそ笑むアイツはそこら中にいるのだッ!



あ。 最後ほとんど羽村市カンケーなかったわ(笑)
そんなこんなで、ようやく自宅へ。
ふぅ〜〜、生還したぞ……!
防災訓練という名のサバイバルから、ようやく我が城(=六畳一間)に帰還。
帰り道、ふと思う。「災害より先に筋肉痛が来るんじゃね?」って。
でも、汗まみれで戻った瞬間のこの達成感! 帰宅して冷たいお茶を一口。
これが今日いちばんの救援物資だな。
今回の教訓
突然起こる災害では、どこに逃げればよいのか? どういった行動をとれば助かるのか? など、正しい行動を選べる人は多くないと言われている。
しかし、事前に訓練を通じて行動手順や避難経路を事前に身につけておくことで、安全に避難できる可能性が高まるのも事実。 例えば、2011年の東日本大震災では、岩手県釜石市の小中学生が日頃の防災教育と避難訓練を活かし、「釜石の奇跡」と呼ばれる高い生存率を記録した事例もある。 日ごろから防災訓練を受けていた小中学生が訓練通りに率先して避難を始め、周囲の大人たちをも導いたのだ! このように、防災訓練は知識だけでなく行動力を養い、命を守る手段となる。 災害はいつ起こるか分からない。 だからこそ、日頃からの準備と訓練が何よりも重要となるのだ、たぶん。
今回は貴重な機会に参加できて、非常に勉強になった。 勇気も、もらった。
そう、この体験を活かして、「俺も今なら世界救えるかも」って思ったんだ。
でも信号渡る途中で足つって、
「あ、俺は自分のふくらはぎすら救えねぇんだ」って気づいた。
今回分かったこと。
隊員たちの過酷な救助活動の裏に、地道なこういった訓練があった。
常に災害に立ち向かう、隊員たちに感謝!
関係者の皆様、暑い中の防災訓練、お疲れさまでした!